どうもおはようございます、ションさんです。
今のIT企業で働き、2025年3月で1年になりました。
最初は多様な技術職への面談で戸惑いもありつつも、無遅刻、無早退、無欠勤で1年働くことが出来ました。
役に立っている実感がある一方で、役に立ててないように感じる時もありました。
そんな中、スーパービジョン(上位資格者から自身の面談の内容を検討・助言をもらう)で「不全感」という言葉が腑に落ちました。
役に立ててないように感じる状態は、「不全感」を抱えながらも相談者を支援することです。
わかりやすく役に立てている自己認識がある場合と違って、つらいんです。
人は自分の行動によって環境が改善されていることや役に立っていることが実感できると、気持ちが上がります。
バンデューラの自己効力感理論の成功体験ですね。
それが感じられないままであっても「相談者の支援を続けることが、相談者の役には立っている」と上位者からはフィードバックをもらいました。
どうしても実感がない中で続けていくと悩んでしまうことがありました。
視野が狭くなっていくんですね。
でも広い視野から第三者目線でのフィードバックで気づくことが出来ました。
そして「不全感」を感じながらも、支援することが相談者のプラスになっていることが多いとも気づかせてもらえました。
相談者ごとに良くなるタイミングや良いと感じることは違います。
キャリアコンサルタントの見方や価値観で見てしまうと、見誤ることがあります。
どこまでも状況を俯瞰して見れる客観的な視野が必要なんですね。
常に自分を客観的に見て自己研鑽に励みたいと思わせてもらいました。
カウンセラーに必要な要素として「曖昧さに耐性を持つこと」です。
白か黒かに決めつけようとし、決めることは楽です。
ですが、世の中には白か黒かで決めることが出来ないことの方が多いです。
「曖昧さ」を受け入れ、「決めないこと」も良しとし、「不全感」を抱きながら前を向く、このようなことを気づかせてくれるキャリアコンサルタントという専門職に感謝しています。
面談スキル向上が喫緊の課題です。
「世話好きの近所の人」とキャリアコンサルタントの違いは理論を根拠に面談を実施することです。
改めてキャリア理論を実践で活かせるように再度学習したいと思います。
クランボルツのプランドハップンスタンス理論、マズローの欲求階層理論、シュロスバーグの転機への対応、ブリッジスの終わりから始まるトランジション理論、ハンセンのILP(統合的人生設計)、この辺から復習していこうと思います。
本日もご訪問いただきありがとうございました~
ブログランキング参加中なんです!ポチッと何卒お願いしますm(_ _)m


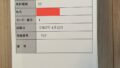

コメント